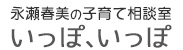コロナ自粛でずっと閉鎖されていた子育てひろばが、7月から再開されました。
市のガイドラインに沿って、予約制で5組ずつ、90分ごとに総入れ替えで、スタッフは消毒作業に追われますが、それでも久しぶりに「会える!」ことをうれしく思います。
壁面装飾の係も、おもちゃの係も、絵本の係も、閉鎖期間中この日のために準備してきました。
七夕飾りには、お願い事の短冊が揺れています。
待ちに待って来所されたお母さんと話し始めると、この間の出来事のあれこれとともに「どこへも行けず、だれにも会えない」なかで感じていたいろんな思いが止めどなくあふれ出しました。
「ああ、やつぱり会って話すと、全然違いますね。聞いてもらうとホッとします。話さないと、自分の中でぐるぐる回ってしまって・・・」
電話とメールでの相談や「オンラインひろば」など、閉所中もできることを模索しながらやってはいたのですが、やはり現実に「会って、話す」のとは全然違うと、私も実感しました。
ですから、幼い子どもたちにソーシャルディスタンスや、会話を控えるようなかかわり方はしたくない。「してはいけない」とさえ、思います。
批判されるかもしれないけれど、感染予防と子どもの心の健康や健全な発達を天秤にかけ、ほどよいバランスをとっていく勇気を、私たちは持たなければいけないのではないかと思うのです。
豪雨災害が予想され避難すべき状況でも、感染を恐れて非難をためらう人が多いという報道に対して、コメントを求められた専門家が、「とにかく災害から身を守ってください。それが優先です。もし感染しても、その時は私たち医師が治療しますから」と応えていたのが印象的でした(うる覚えなので、正確な表現ではありませんが)。
どんなにがんばっても「完璧な予防」はできません。
絶対にかからないように、あれもこれもと予防策に追われて疲れ、親子や夫婦間でぎくしゃくしたり、スキンシップや豊かなコミュニケーション、仲間との交流の機会が失われたりすることが最善なのか、
予防策は大きなストレスなくできる範囲でよしとして、「かかったらかかったで、仕方ない」と割り切る選択は許されないのか・・・
いくら言われても、思わずおしゃべりしたり、群れて遊んでしまう子どもたちに「離れて、離れて!」と言う大人も、言いたい気持ちを飲み込んで「しょうがないよね」と見守る大人もいて、それは仕方ないことだけれど、後者が多いことを願わずにはいられません。
七夕様の短冊に、書いてみようかな・・・
2020.7.5